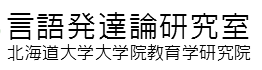伊藤 崇/ITO Takashi
博士(心理学)/Ph.D. (Psychology)
北海道大学大学院教育学研究院 准教授/Assoc. Prof., Faculty of Education, Hokkaido Univ.
職歴
2003.4~2007.3 北海道大学大学院教育学研究科 助手
2007.4~2012.3 北海道大学大学院教育学研究院 助教
札幌学院大学 非常勤講師
北海道情報大学 非常勤講師
北翔大学 非常勤講師
北海道教育大学 非常勤講師
筑波大学 非常勤講師
学歴
1999.4 筑波大学大学院博士課程心理学研究科心理学専攻 入学
2001.3 修士(心理学)(筑波大学)
2003.3 筑波大学大学院博士課程心理学研究科心理学専攻 単位取得退学
2016.3 博士(心理学)(筑波大学)
委員歴
2022年1月-2023年12月 日本発達心理学会 編集委員会委員
2019年10月-2023年10月 日本認知科学会 編集委員会委員
2020年1月-2022年12月 日本教育心理学会 編集委員会委員
2012年1月-2013年12月 日本発達心理学会 国際研究交流委員会委員
個人のブログはこちらから
業績
書籍:単著
- 伊藤崇 (2020). 大人につきあう子どもたち:子育てへの文化歴史的アプローチ 共立出版
- 伊藤崇 (2018). 学びのエクササイズ 子どもの発達とことば ひつじ書房
書籍:共著・共編著
- 伊藤崇 (2020). 言語と思考:言葉のしくみとその発達 川畑直人・大島剛・郷式徹(監修)・加藤弘通・川田学(編著) 公認心理師の基本を学ぶテキスト2 心理学概論:歴史・基礎・応用 ミネルヴァ書房 pp.69-80.
- 伊藤崇 (2019). 子どもは大人を社会化するか 北海道大学教育学部・宮﨑隆志・松本伊智朗・白水浩信(編) ともに生きるための教育学へのレッスン40:明日を切り拓く教養 明石書店 pp.80-83.
- 伊藤崇 (2017). 寄稿 センシングツールで授業が見えた 香川大学教育学部附属高松小学校(編著) 創る:2領域カリキュラムで子どもが変わる!教師が変わる! 東洋館出版社 pp.106-107.
- 伊藤崇 (2013). 学校と教室のしくみ 櫻井茂男・茂呂雄二(編著) 新教職教育講座 第7巻 発達と学習 協同出版 pp.215-231.
- 伊藤崇 (2012). 国語教育――言語に再び出会う―― 茂呂雄二・有元典文・青山征彦・伊藤崇・香川秀太・岡部大介(編) ワードマップ 状況と活動の心理学――コンセプト・方法・実践―― 新曜社 pp.198-201.
- 伊藤崇 (2011). 聖なる出会いに奉仕せよ 山本睦・加藤弘通(編) ひとつ上をいく卒論・修論を書くための心理学理論ガイドブック ナカニシヤ出版 pp.137-146.
- 伊藤崇 (2011). 動いて知る 山本睦・加藤弘通(編) ひとつ上をいく卒論・修論を書くための心理学理論ガイドブック ナカニシヤ出版 pp.1-12
- 伊藤崇 (2011). 「他者」の条件:ヴィゴツキーの美的反応理論から 茂呂雄二・田島充士・城間祥子(編) 社会と文化の心理学:ヴィゴツキーに学ぶ 世界思想社 pp.15-31.
- 伊藤崇 (2007). 「ずれ」から発達が生まれる 夏堀睦・加藤弘通(編) 卒論・修論をはじめるための心理学理論ガイドブック ナカニシヤ出版 pp.12-22.
- 伊藤崇 (2007). 「手段」を手段として精神を描く 夏堀睦・加藤弘通(編) 卒論・修論をはじめるための心理学理論ガイドブック ナカニシヤ出版 pp.92-101.
事典・辞典
- 能智正博(編集代表)・香川秀太・川島大輔・サトウタツヤ・柴山真琴・鈴木聡志・藤江康彦(編) (2018). 質的心理学辞典 新曜社(「意義と意味-ヴィゴツキーによる」「異種混交」「多声性」「発達の最近接領域」「発話」「文化的透明性」「分析単位」を担当)
翻訳
- フレッド・ニューマン,ロイス・ホルツマン 伊藤崇・川俣智路(訳) (2020). 革命のヴィゴツキー:もうひとつの「発達の最近接領域」理論 新曜社
- リチャード・A・アスリン 伊藤崇(訳) (2017). 言語発達:エイマスたちによる/ba/と/pa/の弁別研究再訪 アラン・M・スレーター,ポール・C・クイン 加藤弘通・川田学・伊藤崇(監訳) (2017). 発達心理学・再入門 新曜社 pp.233-248.
- キャリー・ロブマン,マシュー・ルンドクゥイスト ジャパン・オールスターズ(訳) (2016). インプロをすべての教室へ:学びを革新する即興ゲーム・ガイド 新曜社 (伊藤は第4章の一部を担当)
- ドミニク・バドゥーチ 伊藤崇(訳) (2004). ヴィゴツキーの理論を拡張する:生命工学研究室での日本人による社会的相互行為を事例として 石黒広昭(編) シリーズ社会文化的アプローチ 社会文化的アプローチの実際:学習活動の理解と変革のエスノグラフィー 北大路書房 pp.53-70.
論文:査読つき
- 山森光陽・伊藤崇 (2022). 生理心理学的指標や身体運動の計測による教授学習過程研究に関するシステマティックレビュー 日本教育工学会論文誌, 46, 171-182.
- 中島寿宏・伊藤崇・川田学 (2018). 体育授業におけるコミュニケーションの様相:特に中学校ダンス授業におけるグループ学習を中心として 運動とスポーツの科学, 23(2), 125-132.
- 山森光陽・伊藤崇・中本敬子・萩原康仁・徳岡大・大内善広 (2018). 加速度計を用いた小学生の授業参加・課題従事行動の把握 日本教育工学会論文誌, 41, 501-510.
- 伊藤崇 (2015). 幼児による家族内会話への傍参与の協同的達成 認知科学,22,138-150.
- 松本博雄・伊藤崇・常田美穂・三原菜月 (2014). 幼児期における文字表現と文字使用:絵本作り活動における文字の機能から 心理科学,35,53-63.
- 伊藤崇・関根和生 (2011). 小学校の一斉授業における教師と児童の視線配布行動 社会言語科学,14,141-153.
- 伊藤崇 (2011). 集団保育における年少児の着席行動の時系列分析:「お誕生会」の準備過程を対象として 発達心理学研究,22,63-74.
論文:査読なし
- 伊藤崇 (2023). フラットな音と遮断される回路:子どもとデジタル技術の関係をどう記述するか 発達心理学研究, 34(4), 285-297.(依頼論文)
- 伊藤崇・中島寿宏・川田学 (2021). 発達心理学研究におけるセンサを用いた行動認識技術の意義と課題 発達心理学研究, 31(4), 190-200.(依頼論文)
- 伊藤崇 (2019). 日本の異学年教育と香川大学教育学部附属高松小学校の「縦割り創造活動」 子ども発達臨床研究, 12(特別号), 49-54.
- 伊藤崇 (2014). 保育所での活動間移行過程における子どもたちによる呼びかけ行動の分析 子ども発達臨床研究,5,1-11.
- Ito, Takashi. (2007). Multiparty conversations as an ecological environment for language development. Annual Report (Research and Clinical Center for Child Development, Hokkaido University), 29, 11-15.
- 伊藤崇 (2006). ドラマの心理学からドラマ的心理学へ 活動理論ニューズレター, 16, 9-13.
- Ito, Takashi (2006). Participation in family conversation as an addressee: a case study of a four-year-old boy. Annual Report (Research and Clinical Center for Child Development, Hokkaido University), 28, 63-75.
- 伊藤崇・藤本愉・川俣智路・鹿嶋桃子・山口雄・保坂和貴・城間祥子・佐藤公治 (2004). 状況論的学習観における「文化的透明性」概念について:Wengerの学位論文とそこから示唆されること (コメント:高木光太郎 Wenger論文の多重パースペクティブ性) 北海道大学大学院教育学研究科紀要, 93, 81-157.
- Ito, Takashi (2004). Children’s synchronization of utterance in the Japanese preschool. Annual Report (Research and Clinical Center for Child Development, Hokkaido University), 26, 45-55.
- 伊藤崇・茂呂雄二 (2002). 教室環境における言語発達の分析に向けた記述の枠組み 筑波大学心理学研究, 24, 99-110.
- 伊藤崇 (2002). 教育における心理的道具のひろがり:コズーリンのアイディアによせて 日本認知科学会「教育環境のデザイン」研究分科会研究報告, 8(2), 33-39.
- 伊藤崇 (2001). 書き起こせない発話者:一斉発話の中の一人ひとりの声 日本認知科学会「教育環境のデザイン」研究分科会研究報告, 8(1), 20-26.
- 伊藤崇 (1998). 幼児の音韻分解意識と手あそびパフォーマンスの関連 筑波大学東西言語文化の類型論特別プロジェクト研究報告書 平成10年度 I, 293-330.
その他刊行物
- 伊藤崇 (2023). 書評 奥村 高明・有元 典文・阿部 慶賀 (編著) (2022).コミュニティ・オブ・クリエイティビティ:ひらめきの生まれるところ 日本文教出版 認知科学, 30(4), 565-566.
- 伊藤崇 (2023). 手土産考 質的心理学フォーラム, 15, 109-111.
- 伊藤崇 (2021). 保育実践における3つの「理解」:大人につきあう子どもの姿を描くために 発達, 168, 51-56.
- 伊藤崇 (2021). 自著を語る 革命のヴィゴツキー:もうひとつの「発達の最近接領域」理論 心理学ワールド, 93, 43.
- 伊藤崇 (2019). じぶんアクションリサーチとしてのからだメタ認知メソッド 質的心理学研究, 18, 277-280. (諏訪正樹「『こつ』と『スランプ』の研究:身体知の認知科学」(2016年,講談社)への書評)
- 伊藤崇 (2014). 待てない私たちが待つために:7人の発表者へのコメントとして 子ども発達臨床研究,6(特別号),69-72. (コメント論文)
- 伊藤崇 (2011). 養育実践を学校に導入するために 北海道大学大学院教育学研究院紀要,113,21-25. (コメント論文)
- 伊藤崇 (2011). 浜田寿美男著『私と他者と語りの世界』 法と心理,10(1),159-160.(書評)
学会:発表
- 伊藤崇 2024.3.6 スマートスピーカーに話しかけるよう親が子どもに促すこと 日本発達心理学会第35回大会 大阪国際交流センター
- 伊藤崇 2023.9.8 子どもの日常生活におけるスマートスピーカ使用の実態 日本認知科学会第40回大会 公立はこだて未来大学
- 伊藤崇 2023.3.4 子どもの日常生活に埋め込まれたデジタルテクノロジー 日本発達心理学会第34回大会 立命館大学いばらきキャンバス
- 伊藤崇 2022.9.9 子どもの日常生活における電子デバイスの使用実態 日本認知科学会第39回大会 青山学院大学(オンライン開催)
- 伊藤崇・一柳智紀 2016.10.8 授業内容についての想起の仕方と授業中の身体の揺れの関連―「ビジネス顕微鏡」を用いた授業分析の試み(3)― 日本教育心理学会第58回総会 サンポートホール高松
- 伊藤崇 2015.9.18 授業におけるコミュニケーションの暗黙的な次元を探る:ウェアラブルセンサとビッグデータ解析システムの応用 日本認知科学会第32回大会 千葉大学西千葉キャンパス
- 伊藤崇・一柳智紀 2015.8.27 授業内容についての理解の程度と授業中の身体の揺れの関連性-「ビジネス顕微鏡」を用いた授業分析の試み(2)- 日本教育心理学会第57回総会 朱鷺メッセ
- Takashi, Ito. 2015.7.18 Looking Communication in Science Classes through “the Microscope”. presented at The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers. Maruay Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
- 伊藤崇・松本博雄・常田美穂・松田剛太 2015.3.21 人間行動ビッグデータ収集システムによる幼児の鑑賞行動の分析 日本発達心理学会第26回大会 東京大学本郷キャンパス
- 伊藤崇 2014.11.8 授業に参加する児童の身体リズム-「ビジネス顕微鏡」を用いた授業研究の試み(1)- 日本教育心理学会第56回総会 神戸国際会議場
- 伊藤崇・一柳智紀・合田徳夫 2014.9.21 行動計測システム「ビジネス顕微鏡」の授業研究への応用可能性 日本教育工学会第30回全国大会講演論文集,683-684. (岐阜大学)
- 伊藤崇 2014.3.21 年少児のお誕生会準備過程における遊びの発見 日本発達心理学会第25回大会論文集,197. (京都大学)
- 松本博雄・伊藤崇 2013.8.19 幼児期における文字の利用Ⅱ─幼児の絵本作り活動における文字の機能と文字獲得水準─ 日本教育心理学会第55回総会論文集,498. (法政大学)
- 伊藤崇 2012.11.22 小学校国語授業での一斉読みにおける個々人の読み方の調整過程 日本教育心理学会第54回総会発表論文集,11. (琉球大学千原キャンパス)
- Takashi, Ito. 2012.8.29 Historical development of conversational styles in a Japanese family. A paper presented at the International Workshop of JSDP in Tokyo. Taisho University, Tokyo.
- 伊藤崇・関根和生 2012.3.10 授業において児童は発話をどのように聞いているのか(5) 日本発達心理学会第23回大会発表論文集,341. (名古屋国際会議場)
- 伊藤崇 2011.9.16 保育園での一斉活動実践における「日常的実験」 日本心理学会第75回大会発表論文集,1108. (日本大学)
- Takashi, Ito, & Kazuki, Sekine. 2011.9.7 How do elementary students listen to the speech during Japanese language lessons? ISCAR International Conference 2011, Rome.
- 伊藤崇・関根和生 2011.7.25 授業において児童は発話をどのように聞いているのか(4) 日本教育心理学会第53回総会発表論文集,344. (かでる2・7,札幌市)
- 伊藤崇・関根和生 2011.3.27 授業において児童は発話をどのように聞いているのか(3) 日本発達心理学会第22回大会論文集, 672. (東京学芸大学)#1
- 伊藤崇・関根和生 (2010). 授業において児童は発話をどのように聞いているのか(2)――教師と児童の視線配分の関連性―― 日本教育心理学会第52回総会論文集, 761.
- 伊藤崇・関根和生 (2010). 一斉授業において児童は発話をどのように聞いているのか 日本発達心理学会第21回大会論文集, 106.
- 伊藤崇・松本博雄 (2008). 音韻意識の形成過程の多様性を探る試み(3) 日本教育心理学会第50回総会論文集, 10.
- 伊藤崇 (2008). 宛先が不明の発話に4歳児はどう対処しているのか 日本心理学会第72回大会論文集, 1121.
- 伊藤崇・松本博雄 (2008). 音韻意識の形成過程の多様性を探る試み(2) 日本発達心理学会第19回大会論文集, 705.
- 伊藤崇 (2007). 家庭内の会話はどのように組織化されているのか――子どものいる家庭において見られた会話の分析から―― 日本心理学会第71回大会発表論文集, 1080.
- 松本博雄・伊藤崇 (2007). 音韻意識の形成過程の多様性を探る試み――語彙知識との関連から―― 日本教育心理学会第49回総会発表論文集, 317.
- 伊藤崇・松本博雄 (2007). 音韻意識の発達メカニズムをとらえる方法論の検討 日本発達心理学会第18回大会発表論文集, 595.
- 伊藤崇 (2006). 自分が「聞き手」であることを4歳児が知るとき 日本発達心理学会第17回大会発表論文集, 418.
- 伊藤崇 (2006). 音韻意識の生成に関する理論的検討 日本LD学会第15回大会プログラム, 75.
- 伊藤崇 (2005). 4歳児はいかにして会話を組織するか――「聞き手」の獲得に注目して―― 日本教育心理学会第47回総会発表論文集, 36.
- 伊藤崇 (2004). 幼稚園で子どもは一斉に発話するあいだ何をしているのか 日本発達心理学会第15回大会発表論文集, 462.
- Ito, Takashi (2003). Synchronized utterances of children in the Japanese preschool life. A paper presented at the International Workshop of JSDP in Tokyo, August.
- 伊藤崇 (2003). 保育室での「お誕生会」における参加構造の創発と創出 日本教育心理学会第45回総会発表論文集, 574.
- 伊藤崇 (2002). 幼児の会話における引用の多様性と発達――「いらっしゃいませー」と「友達になろうって言ってるみたいって言ってね」―― 日本教育心理学会第44回総会発表論文集, 211.
- 伊藤崇 (2001). 保育園のお集まり場面における一斉発話の相互行為的創出 日本教育心理学会第43回総会発表論文集, 319.
- 伊藤崇 (2000). 幼児の音韻的意識と歌遊びパフォーマンスの関連 日本発達心理学会第11回大会発表論文集, 23.
学会:シンポジウム・ラウンドテーブル・ワークショップ
- 瀬野由衣・近藤龍彰・若林紀乃・大久保智生・赤木和重・常田美穂・伊藤崇・平井美佳 2024.3.6 子育て本を発達研究者が親目線で読んでみた:今,求められる子育て本とは何か? 日本発達心理学会第35回大会 話題提供
- 土倉英志・郡司菜津美・伊藤嘉高・牧野遼作・青山慶・伊藤崇 2020.9.17 文化的実践における認知研究の相互理解に向けて 日本認知科学会第37回大会(オンライン開催) 指定討論
- 青山征彦・石田喜美・松嶋秀明・加藤浩平・松井かおり・伊藤崇 2019.9.21 関係を紡ぐ言葉の力/言葉を紡ぐ関係の力:「言葉する人(Languager)の視点から心理療法・教育・学習を横断的に捉えなおす 日本質的心理学会第16回大会(明治学院大学白金キャンパス) 指定討論
- 山森光陽・伊藤崇・長野祐一郎・神長伸幸・河野麻沙美・楠見孝・有馬道久 2019.9.15 生体情報を用いた教授学習研究の可能性 日本教育心理学会第61回総会(日本大学文理学部) 話題提供
- 坂田陽子・島田英昭・久保南海子・片山敏郎・中島寿宏・伊藤崇・日下菜穂子・楠見孝 2019.3.17 デジタルが変える子どもと高齢者の世界:認知・社会性の発達から社会的ネットワークまで 日本発達心理学会第30回大会(早稲田大学戸山キャンパス) 話題提供
- 岡部大介・郡司菜津美・伊藤崇・上田信行・南部美砂子・青山征彦 2018.11.25 集合的な場の「温度感」を記述する 日本質的心理学会第15回総会(名桜大学) 話題提供
- 伊藤崇 2016.12.11 小学1年生から6年生までが参加する創造的協同活動における対面行動の分析:人間行動センシングツールを用いた調査から 2016年日本認知科学会冬のシンポジウム 認知科学の新展開:テクノロジーの進化は認知科学をどう変えるか? 明治大学駿河台キャンパス
- Takashi, Ito 2016.12.9 Exploration for communication in multigrade classes with the wearable sensory device and the system for big-data analysis. presented at 2016 HU-SNU-NTNU-KU Joint Symposium for Science Education. Seoul National University, Seoul, Korea.
- 一柳智紀・橘春菜・岸野麻衣・伊藤崇・高垣マユミ・鹿毛雅治 2015.8.28 実践から学び,実践に還す-教育実践と歩む教授・学習研究の展望- 日本教育心理学会第57回総会(新潟大学) 話題提供
- 菅野幸恵・亀井美弥子・陳省仁・須田治・岡本依子・伊藤崇・東海林麗香 2015.3.21 文化化としての親の営み,子の営み 日本発達心理学会第26回大会(東京大学) ファシリテーター
- Takashi, Ito. 2014.12.3 Applying wearable sensing devices to interactional analysis of classroom lessons. presented at National Taqiwan Normal University-Hokkaido University-Seoul National University joint symposium on science education & The 17th Hokkaido University-Seoul National University joint symposium-satellite session. Yilan, Taiwan.
- 滝口圭子・伊藤崇・田爪宏二・若山育代・杉村伸一郎 2014.11.7 改めて幼児教育と小学校教育の学びの連続性を問う 日本教育心理学会第56回総会(神戸大学) 話題提供
- 山崎寛恵・森内秀夫・梶川祥世・嶋田容子・丸山慎・志村洋子・伊藤崇 2014.3.21 乳幼児の音楽的行動の発達環境を考える:実践観察と調査から 日本発達心理学会第25回大会(京都大学) 指定討論
- 小島康次・伊藤崇・神谷栄司・茂呂雄二 2014.3.23 ヴィゴツキー=スピノザ・ルネッサンスの行方:《心理学の危機》克服への道を求めて 日本発達心理学会第25回大会(京都大学) 企画・司会・指定討論
- 茂呂雄二・伊藤崇・香川秀太・広瀬拓海・守下奈美子・Schmit, Wagner Luiz・森岡正芳 2013.9.1 遊びとパフォーマンスにもとづいた質的な学習=発達研究 日本質的心理学会第10回大会(立命館大学) 話題提供
- 滝口圭子・田爪宏二・松本博雄・伊藤崇 2013.8.17 改めて保幼小接続を考える─滑らかな接続の意味するところ─ 日本教育心理学会第55回総会(法政大学) 指定討論
- 藤江康彦・比留間太白・伊藤崇・河野麻沙美・當眞千賀子・松尾剛 2012.11.25 教室談話研究の現在と展望 日本教育心理学会第54回総会(琉球大学) 話題提供
- 百合草禎二・森岡修一・伊藤崇・加藤弘通・岩男征樹 2012.3 ヴィゴツキー研究の現在:日本の言語教育改革と「リテラシー」を巡る諸問題との関連で――ヴィゴツキー・シンポ(29)―― 日本発達心理学会第23回大会(名古屋国際会議場) 指定討論
- 赤木和重・村上公也・古里章子・別府哲・伊藤崇 2012.3 特別支援教育における授業づくりの新展開 日本発達心理学会第23回大会(名古屋国際会議場) 指定討論
- 百合草禎二・高木光太郎・岩男征樹・伊藤崇 2011.9 「人間の具体的心理学」を具体化する~刑事裁判のフィールドからの試み――ヴィゴツキー・シンポ(28)―― 日本心理学会第75回大会(日本大学) 指定討論
- 青山征彦・有元典文・香川秀太・伊藤崇・ユーリア・エンゲストローム 2011.7 越境概念の再検討――コミュニティ間の“境界”をいかにとらえるか―― ISCAR Asia & DEE共同企画ワークショップ『状況活動研究の最前線』(大正大学) 指定討論
- 伊藤崇・松嶋秀明・川俣智路 2011.7 学校空間の社会的構造 ISCAR Asia & DEE共同企画ワークショップ『状況活動研究の最前線』(大正大学) 企画・司会・話題提供
- 伊藤崇・関根和生・福田信一 2011.7 教室での身体的なコミュニケーションからとらえる学び 日本教育心理学会第53回総会(北海道心理士会・北翔大学) 企画・司会・話題提供
- 青山征彦・香川秀太・伊藤崇・新原将義・有元典文・森下覚 2011.7 実践のアンサンブルをどう読み解くか――状況論・活動理論の実際(1)―― 日本教育心理学会第53回総会(北海道心理士会・北翔大学) 話題提供
- 松本博雄・大久保智生・陳 省仁・伊藤 崇・加藤弘通・川田 学 2011.7 心理学研究・教育における理論の役割を考える 日本教育心理学会第53回総会(北海道心理士会・北翔大学) 話題提供
- 伊藤崇・関根和生・一柳智紀・秋田喜代美 2011.3 授業を作り上げる児童の言語・非言語的行動 日本発達心理学会第22回大会(東京学芸大学) 企画・話題提供 #1
- 百合草禎二・茂呂雄二・伊藤崇・岩男征樹 2011.3 ヴィゴツキーの心理学と人間学――ヴィゴツキー・シンポ(27)―― 日本発達心理学会第22回大会(東京学芸大学) 指定討論 #1
- 上野直樹・香川秀太・茂呂雄二・杉万俊夫・ジェームズ・ワーチ・伊藤崇 2010.1 流動的なメディア社会のバウンダリークロッシング ISCAR Asia2010(筑波大学) 司会
- 茂呂雄二・森岡正芳・宮崎清孝・田島充士・臼井東・伊藤崇・香川秀太 2009.9 バフチンの対話主義と質的な教育心理学 日本教育心理学会第51回総会(静岡大学) 指定討論
- 丸山慎・石川泰・宮崎清孝・伊藤崇 2009.9 アートに”なる”――認知と活動のコンフリクトから芸術教育を再考する―― 日本教育心理学会第51回総会(静岡大学) 指定討論
- 山口(中上)悦子・茂呂雄二・伊藤崇・土佐信道・宮崎清孝 2008.11 アートな学び――アートを介して生の質を転回する―― 日本質的心理学会第5回大会(筑波大学) 企画・司会
- 百合草禎二・伊藤 崇・岩男征樹・森岡正芳・高木光太郎 2007.9 ヴィゴツキーと解釈学――ヴィゴツキー・シンポ(21)―― 日本心理学会第71回大会(東洋大学) 司会
- 朴東燮・茂呂雄二・佐藤公治・伊藤崇・田島信元 2007.7 相互行為のレパートリーの多様性と社会的変異 ISCAR第1回国際アジア大会(武蔵工業大学) 話題提供
- 百合草禎二・岩男征樹・伊藤崇・森岡正芳 2006.11 エリ・エス・ヴィゴツキーの芸術心理学と人格論――ヴィゴツキー・シンポ(19)―― 日本心理学会第70回大会(九州大学) 話題提供
- 茂呂雄二・佐木みどり・谷垣内和子・城間祥子・佐藤公治・南博文・伊藤崇 2004.3 学びの場を開く――教育実践者と専門家のコラボレーション―― 日本発達心理学会第15回大会(白百合女子大学) 司会
- 宮崎清孝・松嶋秀明・小野寺涼子・鈴木真理子・高木光太郎・伊藤崇・須永剛司・山崎知海・菊地陽介 2002.2 教育環境の中の道具のデザイン:会話のデザインと心理的道具のデザイン 日本認知科学会「教育環境のデザイン」研究分科会シンポジウム(筑波大学) 口頭発表
- 茂呂雄二・佐藤公治・岡田美智男・岡部大介・有元典文・上野直樹・原田悦子・伊藤崇・高橋秀明 2001.6 ワークショップ「発話・行為の分析はいかにあるべきか」 日本認知科学会第18回大会(はこだて未来大学) 口頭発表
その他研究会など
- 伊藤崇 2024.2.28 子どもと家族による会話エージェントへの接近方法:ビデオ映像の観察データから ことば・認知・インタラクション12 話題提供
- 伊藤崇 2023.11.25 成長しないヒロインがもたらすこと 日本認知科学会教育環境のデザイン分科会 研究会『あまちゃん』への/からの接近(招待講演)
学位請求論文
- 伊藤崇 (2016). 集団教育における一対多的参加構造の組織化過程 平成27年度筑波大学人間総合科学研究科心理学専攻博士論文
- 伊藤崇 (2001). 幼児における同期的な発声の相互調整過程 平成12年度筑波大学大学院心理学研究科中間論文(修士論文)
獲得した研究費
- 科学研究費補助金
「詳細」をクリックすると、国立情報学研究所・科学研究費補助金データベースで詳細を見ることができます。- 挑戦的研究(萌芽) 「子どもは電子マネーをどう理解するか:超スマート社会での幼児・児童の生活実態の解明」 2020~2022年度 研究課題番号:20K20796 詳細
- 基盤研究(B) 「教師のファシリテーション能力向上を促す授業カンファレンス・システムの開発と検証」 2019~2022年度 研究課題番号:19H01707 詳細
- 基盤研究(C) 「行動ビッグデータの収集解析技術を応用した授業コミュニケーションに関する実践的研究」 2014~2016年度 研究課題番号:26380865 詳細
- 若手研究(B) 「社会認知的エコロジーとしての教室への適応過程:参加役割の習得に注目して」 2009~2011年度 研究課題番号:21730511 詳細
- 若手研究(B) 「集団内の幼児による会話の組織化過程の微視的分析:参加役割の取得と付与に注目して」 2005~2006年度 研究課題番号:17730377 詳細
- その他
- 平成26年度北海道大学研究戦略室 包括連携等事業経費助成 「人間行動ビッグデータ可視化技術の保育・教育分野での利活用に関する公開研究会の開催」
- 平成25年度日教弘本部奨励金 「協調学習における生徒間の相互作用を即時的に解析するビッグデータ収集・処理システムの開発」 2014~2015年度 助成番号13A2‐008
- 平成25年度北海道大学研究戦略室 包括連携等事業経費助成 「コミュニケーションの可視化技術を用いた保育・教育の効果測定のためのパイロットスタディの実施」